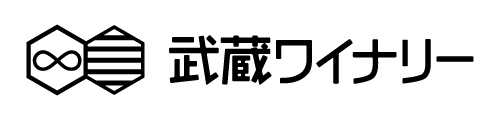武蔵ワイナリーのぶどう栽培

美味しいワインは、美味しいぶどうから!
ワインはぶどうで決まると言っても過言ではありません。
ワインにおけるぶどうの品質は80%とも90%とも言われ、それ以外の比率は10~20%に過ぎません。
ぶどうを栽培せずに、買い付けブドウだけで造っているワイナリーは全く意味が無いのではないかと思い、2011年の創業からおよそ8年間、ぶどう栽培に集中し、良いぶどうが栽培出来なければ、ワイナリー自体を諦める覚悟でぶどう栽培に取り組みました。
農薬や肥料を使わない栽培を目指した結果、常識に反してぶどうを元気に栽培することで、農薬や肥料を使わないことは当たり前に出来る様になり、ぶどう自体が活力に満ち溢れ美味しくなることが分かってきました。
なぜこのように美味しいブドウが育つのか、じっくりとご覧ください。
スタンダードを覆す武蔵ワイナリーの栽培方法
武蔵ワイナリーでは、これまで常識とされていた栽培方法を見直しました。
そのことで、全く根拠なく常識とされているものがあるとも判明しました。
これからお話しすることは、ブドウ栽培の新しいスタンダードになると言っても過言ではない内容です。
雨除けの設置により 農薬不使用栽培を実現
武蔵ワイナリーは最初から農薬に頼らない栽培に特化しました。
私は思うのですが、農薬を使用しない栽培を実現する第一歩はとにかく農薬を使用しないことに就きます。
農薬を使ってから、徐々に減らして農薬不使用を実現した人を私は知りません。
使ってしまったら最後、農薬不使用は実現しないと考えています。
まずは、埼玉県比企郡小川町でも栽培が可能であろうヤマブドウ交配種の「小公子」の栽培を2011年から手掛け、2012年にはメルローも試験栽培を開始しました。
2013年には250㎏の収穫があり最初のワインが誕生しました。2014年は1tを目指しましたが、雨の多い年となり、病気が多発してしまい、170㎏と惨憺たる結果となりました。
雨がぶどうに当たらないようにすることは、安定したぶどうの収穫には欠かせないと判断し、独自の雨除けを開発し、2015年の栽培では1.4tという結果を出し、ぶどうの質も良く、いよいよワイナリーが現実のものとなってきた瞬間です。
肥料不使用栽培(自然栽培)の実現
自然栽培とは肥料を使用しないで作物を栽培することですが、これまで私の知っていた自然栽培は何の根拠も理論も無く、根性論的なまたは宗教的なものと考えていて、全く興味がありませんでしたが、「植物の成長ホルモンを利用した自然栽培」はそれを理論的にしてくれました。
肥料と言えば、N(窒素)、P(リン酸)、K(カリウム)が植物の三大栄養素と言われています。しかし、植物の三大栄養素と呼ばれるものは、植物の成長ホルモンの構成元素としてNは少量存在するものの、PとKは存在しません。Nは空気中にも存在する元素ですから、過剰なほど与える必要があるのか?という疑問が湧きます。
この現実は、根本的には肥料は必要ないという事を裏付けることと言えます。
では、肥料とは何なのか?私の見解は、人間でいう精力ドリンクの様なものではないかと推測しています。元気が無くなってしまったら与えるものです。
つまり、ぶどうを元気に育てれば、肥料は不要だということに辿り着きます。
具体的には、脇芽(副梢)を取り除き1本の枝を太く長く伸ばすことに行き着きます。それにより、太くて長い根を張る事が出来て元気なぶどうの木が出来ます。
そうすることでそもそも元気ですから肥料は不要になります。
美味しいぶどう栽培が実現
植物の成長ホルモンに着目すると、美味しいぶどうを栽培するには「ジベレリン」と言われるぶどうを不味くする成長ホルモンを極力ぶどうが出さない様にすることに行き着きます。
どんな時に植物はジベレリンを分泌するかを調べ、ジベレリンが出てしまう行為をしない様にすることで、ぶどうが美味しくなると思います。ぶどうが不味くなる成長ホルモンをAIに聞くと真っ先に「ジベレリン」の名前が挙がります。
具体例を示すと、「摘芯をする」ことはジベレリンが分泌される筆頭に挙げられます。特に摘芯は垣根仕立ては当たり前に行われますから、垣根仕立てのブドウ栽培は、ぶどうが不味くなると言えます。武蔵ワイナリーでは、摘芯をせずに枝をグングン伸ばします。
武蔵ワイナリーの栽培は、農薬や肥料を使わないだけでなく、結果としてぶどうが美味しくなる栽培方法だという事が分かりました。美味しいぶどうからは当然おいしいワインが出来ますので、将来的には適正な評価をして頂けるものと信じて、美味しいぶどう造りに邁進しようと思います。